鈴木です 「生きてるだけで、愛。」
タイトルが何となく気にくわないなと感じて(今思えばそんな理由で敬遠して本当に危ない、惜しいことをするところだった)、気になりつつも観ないでいいやと思ってたものの、お勧めされたので観てみたら本当に良かった…
感想メモ
※この先ネタバレ注意
こんな風に、世間一般の「強くない」人を繊細に守れる映画を作ってくれてありがとうと。思った。
バイト先でのウォッシュレット のくだりは個人的に、「リップヴァンウィンクルの花嫁」の七海が清掃のバイトをやめるきっかけになった、陰口を耳にしてしまったシーンを強く思い返しながら観た
何が共通してると感じたかというと、
日々の会話や信頼関係はきっと主に共感することで成り立っているものの、誰かと感覚や感情を心から純粋な気持ちで共有できることって実はそれほど簡単なことではない。
だからこそ「上部」や「お世辞」を駆使して上手く成り立つ関係だって事実多くある訳で。
みんなちゃんとそのことには気づいてて、だから多くの人はそれをいかに自然に自分の中に取り込んで、自然に使いこなせるようになるか、っていうことを、多分寧子が全身の毛を剃り落としたという学生の時期ぐらいから、重きを置いて学んでいて。
一方で寧子はそうやって自分を偽っていく術を一切身につけずに大人になるわけだから、津奈木と出会った飲み会でもベロンベロンに酔っ払っても周りの女の子たちにはろくに心配もされないで置いていかれちゃう。
寧子の言葉を借りれば、寧子は「見つかっちゃう」から。
だから、カフェバーのウォッシュレット のシーン、
そんな寧子にしてみればさっきまで同じテンションでちゃんと皆笑っていてくれたのに、ウォッシュレット の話になったら一気にそれまでに上昇していたものがサーッと引いていく感じ、一気に現実に引き戻される感覚、それがもう痛々しいくらい現実的だ。
「ああ、やっぱり見つかっちゃったな」っていう心の声が聞こえてきそうなくらい
リップヴァン…では七海がその違いを「見つけてしまう」側ではあったものの、両者が自覚している社会から見たときの自分の弱点や、普通とされる意思疎通を図ることの苦痛さのようなものは共通していると思う。
(で、私は個人的にこういう描写にめちゃくちゃのめり込んでしまう。。好きというか、その緻密さに感心するし惚れ惚れする)
さらには「生きているだけで、愛。」では
「家族のようなものだから」と寧子に救いの手を差し出してはいるものの、彼女に対し根底からの理解がないカフェバーの人たちと、
津奈木が後に自殺者を生み出してしまうことになる程“ゲスな”記事の存在を認知しつつも何もしなかったこと、、
実は性質だけ見れば両者とも同一なのだというところが1番苦しい。
トドメに、ラストで寧子は津奈木との「理解のできなさ」にも本当に気付いてしまうものだから、こんなにも的確で苦しいこと、なかなか無いんじゃないかなって。
カフェバーの人たちには悪気はないし、むしろ彼らなりの「親切さ」を最大に引き出した上で寧子には接しているし、“ゲスな”記事が世に出るのは、数字が獲れる、つまりはそれを求める人々が多くいるからだし、、
…と、考えるとこの世の中のどうしようもないことばかりに寧子は苦しめられているのではないか?ってふと思う。思いますよね
「けど、そういうことでいちいち傷ついてたらやってられないでしょ? 生きてけないでしょ?」
…こんな風に言い聞かせて切り替えられ「ない」人のための話だ。そう確信してからは、もうタイトルで敬遠してた自分を本当に恥じた。。(2度目)
津奈木が「頭から血を流しながらも走る寧子の着ていた青いスカートが揺れて綺麗だった」と言ったように、
寧子が脱ぎ捨ててゆく身につけているもの、全部ちゃんと拾いながらも全力で寧子を追いかける津奈木の姿が私はたまらなく美しいと思った。

「強くない人たち」が寄り添うのを「自分たちには遠い、あるいは理解のできない弱い人間同士が傷を舐め合っている」と解釈する人もいるけれど、私は寧子や津奈木のような繊細さを持つ人の健闘ぶりを讃えたいよ
ひとつだけ惜しいのは安藤さんかな。。シュールな面白さはあったけれど、全体のトーンに対してちょっと浮遊感がありすぎた気もする。が、それを考慮してもかなりの秀作でした。
おしまい
鈴木です 「親密さ」
濱口竜介監督「親密さ」を観て考えたことを書き連ねる の巻
※ネタバレややあり。引用している言葉は正確ではありません。ニュアンスは間違っていないはずです(覚えられない…)。
映画の感想や考察というより、映画を観て考えたこと、です。
◯言葉という選択
相手と対話をするときに、言葉という選択肢は当たり前のものとして存在する。感情や相手への気持ちを伝える手段として、時には口から発せられ交わされる会話として、また、時には手紙やメールなどの目に見える媒体として。
どのような形態であっても共通する点は、言葉はその存在が確かに確認できる状態にあるものだということだ。
だからこそ便利だし、的確に相手の意図することを理解できる。互いの仲を深めるための、あまりにも一般的なツール。
◯言葉への依存
その一方で、距離や隙間を埋めるために、つまり、「親密さ」を求めるあまり、人は言葉に頼り過ぎてしまうことがある。
相手のことを知りたいという思いが強ければ強いほど、相手が放出した言葉に本来込められたもの以上の意味を見出してしまい、それらが全てだと勘違いしてしまうのだ。
そうして拾い集めた言葉たちを繋ぎ合わせて、自分の中で相手はこういう言葉で編成された、こういう人なのだ、なぜならこの人はこの言葉を発したからだと、勝手に人物像を理由付けて作り上げてしまうのではないか。相手の本当の気持ちを置き去りにして。
◯言葉と思考は必ずしも一致しない
「親密さ」後編でとても印象的だったシーンがある。
別れた男女が後日話をしている。カフェかファミレスか、テーブルには水が注がれた二つのグラスがある。話の内容はなぜ別れるに至ったかというものだ。
ふとした時に、男が女に「今何を考えているのか」と問うと、女は「この水をあなたにかけたら何が起こるのかなって」と答える。
こんなふうに、頭で考ていること=思考と、口から出てくること=言葉とは、必ずしも結びつかないことは実は多い。それでも、人は言葉を信じることに対してあまりにも素直過ぎるのではないか、とさえ気付かされたシーンだった。
さらに驚いたのは、この後、男が女にいきなり水をふっかけるのである。立場が逆だとはいえ、思考がいきなり言葉を越えて現実になったとき、そのあまりの実直さに、私はただただ困惑してしまった。その時また、私は自分も日々いかに言葉をなぞって安心しているのかに気付いたのだった。ついさっき言葉を過信している、と自覚したばかりなのに。
◯敬語、という言葉
日本語の特徴でもある敬語。相手を敬い、敬意を示すために用いられる、社会で必須な特殊な言葉。通常、使われた相手は使った人に対して好感を抱く。つまりは、相手を不快にさせないための言葉。程よい緊張感も纏っている。
また、敬語のもう一つ持ちうる特徴としては、「他人に対して使うもの」ということ。特に相手を敬うわけではないものの、初対面の相手には敬語を使うことで、程よい距離感を保つために活用される。
こういったプラスの面に反して、マイナス面としては距離感がなかなかうまく掴めない、あるいは、近づけない、上手く打ち解けられない雰囲気が蔓延してしまう、という点が挙げられる。
なので、距離が近づいてきた、と感じた時に「敬語やめませんか」と提案する人や、最初から「敬語禁止で!」という人などもいる。
映画の中でも、印象的な敬語の使い分けが3つあったので記録しておきたい!
◯敬語の使い分け
一つめは、別れた途端に女が男に対し敬語を使い出し、また、それに気付いた男が敬語に対しつっかかるシーン。
女は「昨日までとは別人だから」と弁明するが、男にはまだ女が好きな気持ちが残っているので、女から明確な言葉ではないものの敬語を使うという行為によって距離を取られたことを感知したのだ。
二つめは、良平の妹が、初めて会った年上の佳代子に夢中で話しながら、ふいに「敬語やめますね」と一言だけ挟み、元の話題へ何もなかったかのように戻り話を続けるシーンだ。
しかも、その後もところどころ無意識のうちに敬語が入り混じった話し方を彼女はする。
距離を必死でつめようとする気持ちの表れがすごく自然で、関心してしまった。
三つめは、良平の妹が想いを寄せる相手に書いた恋文だ。いつものおちゃらけた、軽い感じとは違う、でも嘘のない素直な言葉が綴られてゆく。
あのシーンを回想しながら、自分も手紙を書くときはどうしても真剣に書くなぁとふと思う。口調も敬語あるいはかなり落ち着いたトーンを思い浮かべながら筆を進める。
手紙がそういうものだ、と認識しているからなのだろうか。だとしたら、言葉が媒体として形を纏うときには、その形の在り方によって、同じ思考から出発した言葉でも、最終的にはそれぞれ違う意味に行き着いてしまうのかも知れない。
◯言葉の受取手
更にそれだけではなくて、それぞれの言葉が誰に、どのように受け取られるかによって、言葉に込められた意味は大きく変形してしまうこともある。
暴力の詩のなかで、
「暴力は暴力が振るわれただけでは成立せず、暴力を振るわれた人がそれを暴力だと認識したときにそれは真の暴力となる」というものがある。
それは言葉も同様で、同じ言葉を浴びても、10人いれば10通りの受け取り方があっておかしくないのだ。
1人は100%発信した人の思考を理解したとして、別の1人はその元の思考とは全く違うものとして受け取ったとしても、それは自然なことなのだ。
こう考えたときに、自分が意図した思考を正しく言葉に変換して、それを更に相手が正確に理解してくれる、という言葉のコミュニケーションは、めちゃくちゃ難しいものなのでは。。と、思う。し、言葉には限界があるのだ、と痛感する。日々当たり前のように成立している会話たちが、ものすごい有難いことに思える。
◯言葉以外でも「親密さ」を深める
だから、言葉以外のものにもっと目を向けようと思った。
「今日会ったばかりだけれど、佳代子が自分のことを好きだということが何となくわかる」ように、言葉にしなくてもわかってしまうことは大抵私たちの生活の中で大切なことなのだ。
しかも、言葉にならない思考たちは、敬語だとか、一緒にいる年月だとか、そういう他の要因に一切影響されないで、ちゃんと届くものなのだから。例えば、別々の電車に乗って互いに大きく手を振ったり、バカみたいに投げキッスなんかしたりすることで。そのためには、正しい「想像力」が必要なんだなきっと。
◯変わることと変わらないこと
「変われ変われっていうけどさ、なんで変わらなきゃいけないんだよ」
「じゃないといっしょにいれないからだよ」
「俺だけかわらなきゃだめなのか?」
の喧嘩のシーンを受けて
言葉はそのまま変わらずに居続けることができるが、人は違う。例えば学生から社会人になればそりゃ~変わる。
だから、2年前にはぼそぼそと話していた良平も、軍隊に入ってきっちりとしたお辞儀をして、大きな声ではきはきと話すようになる。(ぼそぼそのときは本当にたまに何て言ってるのか分からなかった。。)
人は気づかぬうちに流れるように変わってしまうのだ。なぜか。それは変わらずにいようとするからこそなのかもしれない。
その場に居続けようとすればするほど、流れに反抗した分変形してしまう。
だから変わらないでほしいと願う気持ちは正しいし、あまりにもかなしい。誰もがおそらくそれは不可能だとわかっているから。
流れ、というのは環境の一言だけで定義できるものではなく、それは例えば日々交わされる会話や、テレビでたまたま目にして知ったニュースだったりする。
「変わってほしいんじゃなくて、ほんとうは、変わらないでほしいだけなのに。」とぽつりと呟かれた令子の言葉があまりにも的確で、私は苦しかった。。
◯精神と肉体
劇団員に令子が行う「あなたは私ですか?」インタビューの中で
「あなたが怖いものは?」という質問に対し
「周りから疎まれること。自分は流されやすいというか、良い意味でも悪い意味でも。」という答え。
「あなたが一番信頼出来る人は?」に対しては、
「兄貴。命を助けられたから。
自分も誰かにとってそんな人になりたい」という答え。
恐怖=精神的なもの、
信頼=生死
に結びついていると考えると、
あれ、逆じゃないのか?と思えてくる。
つまり、精神や思考の表れでもある言葉は信頼には値せず、寧ろ恐怖の火種ともなり、肉体に影響する生死問題は、恐怖ではなく救われることで信頼をもたらすものとして存在する、とこの劇団員は回答している。
肉体の恐怖がイメージとしては先行しがちだけれど、いかに根の部分では精神やそこから生まれる思考、そして精神から出発する言葉が影響力を持つのか、再確認した。
まだまだ書きたいことはこの映画については山ほどある…けど今日は?ここまで
キネカ大森からの帰りの電車で、何も考えずに乗り換え検索したらまさかの大森から京浜東北線、田町で山手線乗り換えで、ひとり電車の中でじんわりしてしまったのでした。。
完
鈴木です
暇なので、「人はなぜ整形に否定的なのか」について考えてみた。
これだけ整形が普及してきた今でも、何となく世間に固定され続けているぼんやりとした概念として、「整形はよくないこと」という考えがある。
私自身もそれには同意見で、母親が「今度こそ天然だと思ったら、あの女優もやっぱり整形らしい」といえば「裏切られた!」と騒いだり。
それでも、「ではなぜ整形はいけないのか」と聞かれたら、これ、という答えが出ず、ずっとモヤモヤしていた。ので、つきつめて考えた末に私なりの答えに辿り着いた。
まず、整形は美しくなるためにするもの、という大前提がある。
整形をする人は、「自分がこうなりたい」っていう顔をデザインして、計画的にそれになる。確かな意思を持って。
つまり、整形後の自分の美しさを、しっかり自分で自覚しているということ。
そもそも美しさが何かって考えたときに、個人的には、、美しいということは大前提として、その上で本人が自身の纏ってる美しさに対していかに無自覚であるか、が大事だと思っていて。
外見を褒める時に、「ミステリアスな」っていう形容詞があるけど、その感覚もちょっと共通してる気がする。
自信に溢れている訳でもなく、ただただ不明な感じ。それは自分に対しても。
一方で、整形で成り立った美しさは全て意図的につくられたものだから、「無自覚さ」が一切ない。
むしろ、本人が思う美しさをただ見せられているだけ、という表現が適切な気がする。
整形でなくとも、例えば自撮り写真ばかりをあげている人をネットで見た時に無意識のうちにむけてしまいがちな一種の冷たい視線も、彼らにこの無自覚さが欠如していることが原因だと思う。
フィルターで良い自分を演出して、その中でも一番良い自分を選りすぐり、自分が納得できる自分を見てもらうためにインターネットに放出する作業。
こういう作為的な美しさに対して、無自覚の美しさは、「見られること」「美しいと思われること」を目標としていないものの、完全に「見られる」「美しいと感じられる」対象となってしまう。
さらにその過程は、本人が本人の美しさに無自覚だからこそ、自分自身の努力や計算によってではなくて、完全に「見る」他者たちによってつくられていくもの。
この他者の「見る」行為の積み重ねが、天然の美しさを更に手の届かないもの、絶対的価値のあるものへと強化するんじゃないか。って考えている。
だから、整った顔をした物心つく前の子供を見ると私はどうしても感動してしまうし、大人ならば、美しいな素敵だなって人ほどインターネットで自分を喜んで晒してなんかいない人であればあるほど見入ってしまうなぁ。
最後はちょっと整形とはちがう話になってしまったけれども(笑)、それでも根底にあるものとしては同じだと信じている。
すっぴん美人が良い、化粧は薄めが良い、っていう概念にも通じるものがあるのかもー。
言語化できてスッキリしたので寝る。
おしまい。
鈴木です 「君の名前で僕を呼んで」
昨日、2回目を観てきた(恥ずかしながら1度目は画と俳優陣の美しさを追うことで精一杯だった、、)ので感想や考察を書きます。
◯あらすじ
1983年夏、北イタリアの避暑地。17歳のエリオは、アメリカからやって来た24歳の大学院生オリヴァーと出会う。
彼は大学教授の父の助手で、夏の間をエリオたち家族と暮らす。はじめは自信に満ちたオリヴァーの態度に反発を感じるエリオだったが、まるで不思議な磁石があるように、ふたりは引きつけあったり反発したり、いつしか近づいていく。
やがて激しく恋に落ちるふたり。しかし夏の終わりとともにオリヴァーが去る日が近づく……。
(公式サイトより引用)
※ネタバレあります。また、時系列や台詞など、もしかしたら違うところもあるかもしれません。見逃してください。。
◯感想をストーリーに沿って。
⑴エリオのオリヴァーへの視線
この映画の見どころのひとつは、主演のティモシー・シャラメ演じるエリオの視線の動きと言っても良いんじゃないか!ってくらいには見応えがあった。
映画は、主人公エリオとその女友達のマルシアがエリオの部屋からオリヴァーの到着を見届けるシーンから始まる。
車の音に気付き、「侵略者だ」とふざけるエリオ。

車から出てきたオリヴァーを一目見て、
「自信家っぽい」と小馬鹿にした感じで第一印象をマルシアに言い、笑う。

何日かをオリヴァーと共に過ごした後も、
「彼の(英語の口癖の)“later”って、横柄だよね」とこぼす場面も。
その一方で、お父さんが毎年インターン生に仕掛けるテストの最中にふと見せる不安と期待が入り混じったようなオリヴァーへの視線や

パーティーに行きオリヴァーが女の子と親しげに踊っているのをやや不満げに見守る視線、

オリヴァーに街を案内した後、「じゃあ」と置いていかれてしまった後しばらく彼を見つめたまま呆然とするような表情と視線、

他にも、父さん・オリヴァーの研究フィールドトリップにくっついていったときも

オリヴァーのうしろを歩きながら嬉しそうに盗み見していたり。

こんな風に、エリオの視線が豊かに揺れる揺れる。。
視線の端っこには常にオリヴァー。
「認めたくはないけれど、どこか気になって仕方がない」エリオの心が、くるくる変わる瞳に映されているかのよう。
そんなエリオの視線は、オリヴァーと気持ちが通じ合ったあとはこうなる。

オリヴァーを正面から真っ直ぐ見られるようになっただけじゃなくて、もう、表情も全く違う。これにはエリオの内面の変化や成長も伴っていると思っていると思います(⑶で詳しく書きます)。
そして、、

この汽車の別れのシーンが個人的に素晴らしかった。
今までのエリオの視線の多さに反し、このシーンの彼は後ろ姿のみ。どんな視線・表情をしているのかは全く分からないのです。。。が、それが物凄く良かった…
心の底ではどんな顔してるのかみたい気はするものの、見えないからこそあの別れの後ろ姿の切なさが引き立つ。これが引き算の美しさだ…と、唸った。。
⑵オリヴァーのエリオへの視線

映画の序盤はほとんど⑴のエリオのオリヴァーへの視線が多いことから、序盤では私たちもあまりオリヴァーの視線を見ることができない。そもそも、オリヴァーはあまりエリオのことを見つめてもいない。
そんなオリヴァーの視線を補う要素としてあるものは、彼の社交的な性格だったり、美しい筋肉質で大きな身体や金髪だったり。それくらい。

前半にオリヴァーの視線が少ない、というかほぼない?ことのひとつには、オリヴァーの出生や過去が謎めいていることも絡んでいる気がする。
オリヴァーのエリオへの唐突ともとれる「優しいことを言ってくれるね」という言葉や、「(僕が同性愛者だと知ったら)僕の両親なら即矯正施設行きだ」という言葉も、
違う国アメリカからやって来たオリヴァーのこれまでが、明るく社交的なキャラクター通りという訳ではなさそうだ、ということを暗示しているのでは。

そんな彼の視線は、特に二人が交わりあった後から大きく変化し、オリヴァーのエリオへのまなざしが一気にその存在感を増してくる。
(↑このとき、「あ、オリヴァーってこんな顔するんだ。」とグッときたのは私だけではないはず。)
それらは、エリオが出会って間もない頃に“横柄だ”と表現したようなものではなく、むしろどこか不安げで刹那的でもある。

だんだんと、オリヴァーは「追われる側」から「追う側」へと変化してゆき、しまいにはエリオには「昨日のこと(交わったことを)後悔していないか」と心配そうに口に出して尋ねるシーンも。

オリヴァーは、キャラクター込みで第一印象が“自信家”だっただけに、だんだんと彼が繊細になっていくその推移が、人を好きになってしまったときのどうしようもない感じを素直に表していて、それがとても純粋で。
観ていて、そうなってからのオリヴァーが私はとっても好きになった。
恋愛には、直接交わされる言葉はもちろんだけれど、恋や愛が実るまでの間には想い人には届くことのない、交わされない言葉が沢山あって、それらを代弁するもののひとつが視線であって。
もどかしい気持ちや気づいて欲しいような気づいて欲しくないような気持ち、それらが全部目に現れると言っても過言ではないと思っている。ので、この映画ではそれらの視線をひとつひとつ汲み取って綺麗に映像化してくれたので、それがとても納得がいった。



⑶エリオの変化
⑴⑵とも被るけど。。
エリオは、読書をしたり曲を作ったりするのが好きで、友人との集いにも気が向かないと行かないこともあるような、内気な性格。

映画では、エリオの言葉を代弁するかのように、オリヴァーへの高まる気持ちが良くピアノで生き生きと表現されている。

オリヴァーへの気持ちをピアノやギター、メモに書いた言葉などにぶつけていく姿も印象的。

↑アメリカのザ・ティーンエイジャーの女の子の日記みたいなかわいいメモ。
エリオとオリヴァーが街に出かけた際、
オリヴァーが前を歩いて街の人たちに親しげに挨拶をしたり、一緒にポーカーを楽しむ一方で、エリオは挨拶もできないし、自分から特別親しくない人の輪の中に入っていくことはできない。
遠くからオリヴァーを見守り、「いつの間にそんなに仲良くなったの?」と聞く。自分にはそんなこととてもできない、とでも言うかのように。

そんなエリオの成長ぶりがよく分かるシーンがある。
オリヴァーと結ばれた後に出かけた先で、
自分から「喉乾いた?」と尋ねながら前を歩き、見知らぬ住人に「お水をくれませんか」と話しかけるのだ。
これが、⑴でも触れたエリオの注目すべき変化である。
さらには、そんな言葉が少なかったエリオが、「告白すべきか 命を絶つか」と考えた末に、オリヴァーに「沈黙が苦痛だ 話がしたい」とまで自ら伝えるようになる。これって物凄いことだと思うのです。
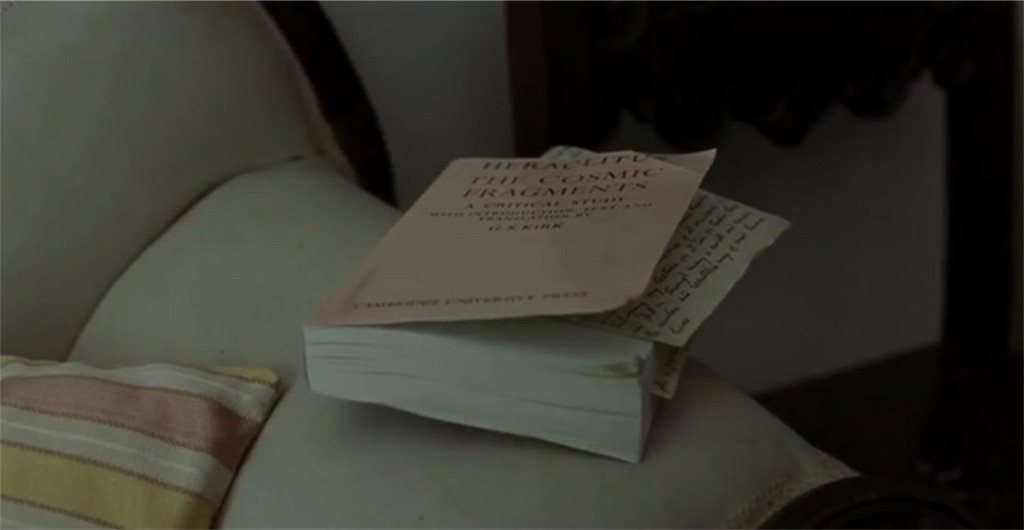
「自信がない」と言っていた自分の殻にこもりがちだった彼が、自ら自分の考えや言葉を外に出したいという欲求を抱くようになることが。

では、、具体的に何が彼をそんな風に変えたのか?と考えた時に
⑷「君の名前で僕を呼んで」
に辿り着くわけです。
正直、この要素がなければ「単純に美しい純愛物語」で完結してしまっていたような気もする。
タイトルにもなっているくらいなのでオリヴァーがエリオに囁くこの言葉の意味を自己流で深掘りします。
①彫刻
まず、映画のオープニングや考古学の研究で印象的だった彫刻。

「官能的で大胆すぎるともいえるカーブが見る者の欲望を誘発する」という感じのコメントをお父さんがしていた男性の彫刻は、
24歳という年齢で、まさに今、美しさの絶頂にいるオリヴァーのよう。
お父さんの言葉をそのまま当てはめれば、17歳という多感な時期にいて、自身の性的なエネルギーを持て余していて、なおかつ、それをどう処理したら良いのかもよく分からないエリオにとって、セクシュアリティをそのまま体現したようなオリヴァーが、誘発装置になったと受け取れる。

更に彫刻でもう一つ印象的だったのが、フィールドトリップで海の底から発見したこの彫刻。

スライドショーで見ていたものよりもやや若く、あどけないような雰囲気が残るこちらの彫刻は、一方でエリオを象徴しているのでは。
このフィールドトリップの前にエリオのやきもちのせいで何となく険悪な雰囲気だった二人は、この彫刻がきっかけで仲直りをする。

この彫刻がバラバラの状態で見つかっていることにも注目で、「海の底に沈んでいた壊れて離れてしまっていたものが一つになる」=「結ばれるべき二人が二人の気持ちを通じあわせはじめる」ことの暗喩ともとれる。
さらに、この日「エリオ!」「オリヴァー!」と、互いの名を呼びあうシーンが挿入されていることも、のちの「君の名前で僕を呼んで」への布石。
モチーフとしてこのような彫刻が使われたことには、オリヴァーが「変化し続けながらも同じであるということ」と評したように、時代を幾度超えていっても、それが普遍的である、ということで「愛」と共通するからなのかな。
②エゴイスティックに自身を相手に重ねて追いかけるということ

①でオリヴァーが美しさを全うしている、美をそのまま体現したような象徴的な存在だと説明したが、同時にそれは「今いる場所を過ぎれば衰えてゆくのみ」ということも意味する。
(ラストシーンのお父さんの言葉にも、「身体はのちに誰も見つめてくれなくなる」というものがある)
たまに見せるオリヴァーのどこか刹那的な視線も、自身でそのことを理解しているからこそなのでは。
だからこそ、自分よりも若い17歳のエリオに、どうにかして自身を重ね、求め、エリオにも自分自身にも縋り、最後の美しい自分としての恋愛をおそるおそる確かめながら噛み締めている様子。そんな感じがした。

一方でエリオはというと、⑶で書いた通り、内向的で自信がない。友達もいるけれど、一人で何かに没頭するのが好き。
そんなエリオの前に現れたオリヴァー。社交的で明るく、誰にでも挨拶ができて、すぐに打ち解けられる。身体は大きく筋肉質で健康的。まさに自分とは正反対で、自分が欲しいものすべてを持っているような男。
憧れからくる嫉妬心で最初は反発しようとするものの、徐々に彼を欲し、同時に、エリオもオリヴァーに自身を投影するようになっていく。また、そうすることでエリオの内面やキャラクターも微妙に変化・成長していく。

このシーンがまさにその象徴で、逆さに映った二人の横顔、そして囁かれる「Call me by your name and i'll call you by mine.」という言葉。そして、呟かれる「エリオ」「オリヴァー」という言葉。
二人が身体で交わることも勿論だけれど、精神的にも溶け合って一つにいくことが決定的に分かる。
互いに向かって自分の名を呼ぶこと。それは酷く利己的なことにも思える。
それでも、「parce que c'était lui parce que c'était moi (それは私だったから。それは彼だったから。)」という言葉のように、
お互いに「その人」しか自分のなかで欠けていたところに当てはまる存在はいなくて、
お互いがいてこそやっと自分が生きる世界に対峙できるようになるのだ、と考えられる。

別れの汽車でオリヴァーを見送った後のエリオが暫く駅でひとり動けず、お母さんに迎えを頼まなければ帰れないほど沈み込んでしまっていたことも、
「一度ひとつに完成した自分の心がばらばらに引き裂かれてしまう」感覚を思えば頷けるし、私も一緒に汽車を見送りながら泣いた…。
他にも、「僕だけの場所だ」とエリオがオリヴァーを秘密の場所に案内することも、二人が融合してひとつになっていることを意味していると思う。
ここの草むらであの美しい初キスも起こったので。

二人が最後に一緒にいった旅でも、ずっとお互いのことを自分の名で呼んでいたのも印象的。

ちょうどエリオの髪で、実はオリヴァーの顔が見えていないということが、二人が二人で一人、ということをこのポスターからも読み取れるので、素晴らしいと思いました。
⑸エンディングについて
夏が終わり、オリヴァーが去っていき、冬になってハヌカの時期にかかってくるオリヴァーからの電話。
エリオは「なんとなく2年くらい続いてた相手と来年結婚するかも」とオリヴァーから告げられる。
電話越しに、エリオはオリヴァーに「エリオ」と呼ぶと、オリヴァーは「オリヴァー」「何一つ忘れない」と告げる。

夏の間のオリヴァーの言葉に、「君には何一つ後悔してほしくない」というものがあったが、これはこのことを暗示していたのかもしれない。

お父さんの言葉の、「知らぬ間に心が衰えてしまう」ように、若い、アプリコットのような時期が過ぎゆくうちに、世のいう常識などにみずみずしい心が殺されていってしまうことを。
こう考えると、この物語は
・お父さん「経験することなく、諦めてしまった人」
・オリヴァー「経験し、諦めてしまった人」
・エリオ「経験し、これからを選べる人」
という三つの立場からも考えられるのです。
それにしても、あの長尺のワンカットエンディングは衝撃的に美しかったなぁ。

⑹その他
・彼の口癖の「later」って横柄だよねとエリオがイタリア語でいうが、それに対してお父さんは横柄だとは思わないな、とあえて英語で答える。それに拗ねながらも英語でかえすエリオ…など、家族間で交わされる言葉の豊かさ!純粋に感動したし、会話の内容以外にも、どの言語で話すかということも各シーンを彩る要素として確立していた点が良かった。
・街を案内したときにチラッとエリオが見ていた青いバスで二人が後に旅に出ることになったことも気付いて嬉しかった。

⑺まとめ
この人しかいないのだという相手に出会い、心も身体も愛して、それでもまた相手を求めて、更には互いに自分を相手に重ね合わせて呼び合う。
それがどんなに完璧でも、自分が「自分」を手に入れることは絶対にできない。手放してまた自分ひとりとして歩いていかなくてはいけない。でも、「何一つ忘れない」。それは「変化し続けながらも同じであるということ」。
だからこの映画の終わり方はとても潔くて美しかった。
こんな相手に出逢ったものなら、言葉を発したいと思っても、名前だけでも十分なのかもしれないな。
一人の少年と一人の青年の、そんな美しい過程をこの映画には観た。

おしまい
鈴木です 「婚約者の友人」
フランソワ・オゾン監督の「婚約者の友人」のあらすじ、感想、個人的な考察です。

※ネタバレあります。また、時系列や台詞など、もしかしたら違うところもあるかもしれません。。
・あらすじ
時代は1919年のドイツ。戦後の傷が癒えぬこの国で、婚約者を戦争で失ったアンナも悲しみ嘆く大衆の1人。
映画は死んだ婚約者のフランツの両親と共に暮らしている彼女が、市場で今は亡き夫のお墓に供えるための花を市場で買い、墓地に向かうシーンから始まる。
墓に着くと新しい花が手向けてあることに気付き、管理人に誰だったのかを尋ねると「フランス人だ」と憎らしげに伝えられる。
次の日も墓に向かうと、彼女はフランツの墓前で涙を流す見知らぬ男を目にする。

その後アンナの家を訪ねてきたアドリアンと名乗るフランス人の男は、確かに昨日も今日もフランツの墓にいた人物であり、自分はフランツの友人だったと話す。
アドリアンがフランツとパリで共にルーブル美術館に出かけ、2人して熱心にマネの絵に見入っていたという話や、アドリアンがパリ管弦楽団で培ったバイオリンの演奏技術をフランツに教えたのだという話を聞き、フランツの両親とアンナの心は少しずつ悲しみから解放され、癒されていく。

その後も舞踏会や海への散歩に一緒に出かけ、アドリアンとアンナは親しくなるものの、とある夜アドリアンはフランツの墓前で今までの話は全て嘘で、自分こそがフランツを戦場で殺した人物であり、自分はただ許しを乞いにここまで来たのだ、自分は明日の汽車でパリへ戻るとアンナに告げる。
アドリアンはその前に自分からフランツの両親にも真実を話したいと願い出るが、アンナが私が代わりに全て伝えると説得する。しかし、彼女は2人には「彼は母の急病で帰ることになってしまった」と説明しただけで、フランツの最期とアドリアンの嘘については触れていないのだった。
そしてアドリアンはパリへと帰っていった。
アンナはその後アドリアンにあなたのことをもう許すという手紙を出すも、手紙は届かず住所不明で戻って来てしまう。
そこでアンナはアドリアンを追いパリへ向かい、苦労の末彼が母親と共に暮らす大きな屋敷に辿り着く。
再会を喜び散歩に出かける2人。アンナは フランツの両親ももうアドリアンのことを許していると嘘を伝えると、「一番嬉しい言葉だ」と喜ぶ。
ドイツで彼がついた嘘について尋ねると、「そうだと思っていた方が幸せなこともある」とアドリアンは言うのだった。

散歩から屋敷に戻ったアンナは、屋敷で夜開かれるパーティーで歌う予定だというファニーを紹介される。ファニーとアドリアンとの仲睦まじい雰囲気を察したアンナは軽く失望するも夜のパーティーに参加する。しかし、パーティーに参加したことで「自分の居場所がない」と確信してしまった彼女はその場から逃げ出してしまう。
追いかけて来たアドリアンは去ろうとするアンナを引き止めるも、口付けを迫られると「ごめん」とだけ言い残し、部屋を去っていってしまう。
翌朝アドリアンの運転でドイツ行きの汽車が発つ駅まで送られるアンナ。アドリアンはファニーは幼馴染であり、彼女と結婚すれば母親も喜ぶ、と話す。
駅に着くと一ヶ月後に控えたファニーとの結婚式に是非来て欲しいとアンナに言うが、「無理よ」と断るアンナ。暫く見つめあったあと、2人は静かに唇を重ねる。「もう手遅れなの」と言い残し汽車に乗り込むアンナ。遠く小さくなっていくアドリアンの影…
その後フランツの両親に届くアンナからの手紙には、アドリアンに会えたこと、彼が元気なこと、パリ管弦楽団に復帰したこと、そして、暫くはまだパリに留まるということが書き記されていた。
ラストは、ルーブル美術館でマネの例の絵の前で、見知らぬ男性に「この絵が好き?」と尋ねられたアンナが、笑顔で「好きよ」と答えるシーンで締めくくられている。
・考察
⑴モノクロ、カラーの使い分け
何と言ってもこの作品の見どころの一つでもある、色の使い分け。
カラーだったシーンをざっと思い出してみたところ、
アドリアンと散歩したとき、アドリアンにアンナが戦争の傷のことを聞いたとき、アドリアンとフランツがルーブル美術館にいったとき、戦場でアドリアンがフランツを殺したとき、アドリアンがフランツのバイオリンを弾いたとき…
と、つまり「アドリアンを通してフランツのことを思い出しているとき」に画面に色が宿っていたように思える。

さらに忘れてはいけないのはラストのマネの絵を「好きよ」と答えるシーンもカラーだったことなのですが、、これについては⑸にて後程述べます。
また、印象的だったのはアドリアンとの舞踏会のシーン。ここでは、華やかそうなのに全くカラーにならない!それはアンナがあの舞踏会の間はすっかり求婚者はおろか、フランツのことを忘れてしまっていたからだと考えれば自然。つまり、あの舞踏会でアンナは「婚約者の友人」に決定的に恋してしまったのだと。
⑵ アンナとフランツは本当に愛し合っていたのか?
何も情報のない冒頭のシーンで最初に観客が目にする、白い花を買い墓地まで歩みを進めるアンナの姿は、凛としていて、そこにはどこか無駄なものが削ぎ落とされた心地よさのようなものすら漂っているように感じた。
さらに、フランツの両親が感情や表情を通しフランツの喪失を体現する場面はあるものの、アンナのそれは単調すぎるように感じられた。
また、アンナがパリへ旅をした際に「フランツが泊まっていた」という宿は娼婦宿のような場所であったことから、彼が浮気していたことも予測できる。
つまりは、結婚前で既に2人の関係は乾いたものになってしまっていたことが垣間見られる。
⑶「青い顔をして仰向けになった男の絵」
アドリアンは多くの嘘を語るが、その中に一つ紛れ込んだ謎がこの言葉。
ルーブル美術館をフランツと訪れた際に、僕ら2人でマネの青い顔をして仰向けになった男の絵に見入っていた、と話したアドリアン。後にアンナがこの絵を目にした時、絵のタイトルが「自殺」であったことを知り、驚く。
⑷「自殺」から読み取れること アドリアンの場合
ではこの「自殺」が何を意味するのか。
アドリアンから考えてみるとすると、「自殺」とは彼にとっては「自分の意思を放棄する、殺すこと」なのではないか。
それは、アンナに自分がついた嘘に対して語った「そうだと信じていた方が例え嘘でも良いことがある」という言葉や、「ファニーと結婚すれば母親も喜ぶ」という言葉から、彼が彼自身の意思で生きること、選択することを諦めていることから推測できる。
さらに、皮肉なことに唯一彼が意思を持って行動した末に手にしたものは、フランツに銃口を向け、引き金を引くこと、そしてフランツを殺すこと=全ての終わりであり、何の始まりでもなかったのだったのだから。
そこで自分の体の下に発見した、死んで青い顔をした仰向けになり横たわるフランツの姿。それはまさにマネの「自殺」の構図と同じだった。

だからアドリアンは、自戒を込めてフランツに関する「嘘」の中に「事実」を紛れ込ませたのではないか。
そもそも、あの嘘が彼にとっては精一杯の本当だったはず。(彼の不安定さは「精神病院にいた」という自らの発言からも分かる)
⑸「自殺」から読み取れること アンナの場合

⑵でも述べたように、どこか違和感のあるフランツとアンナの「愛」。
フランツについては正直情報が少ないので確信はないが、アンナに関しては、二つ大きな決め手がある。
一つ目に、アンナもアドリアンの「そう信じていたほうが幸せなこともある」という言葉を無意識的に信じ、実行している点。彼女の場合なら、「フランツを心から愛していたとする方が幸せ」と。
婚約者の両親に、婚約者の死についての嘘をついただけでなく、その後もパリで起こったこと、そして恐らくこれからの滞在で起こることも、全て彼女はかなしい嘘で塗り固めていく。
フランツの死を起点として「嘘」に頼るしかなくなったアンナは、「真実」、そして「フランツ(への愛)」に対して「自殺」した=「完全にそれを手放し、諦めた」も等しいのでは。
二つ目は、言うまでもなくラストシーンで「自殺」の絵を笑って「好きよ」と答えるところ。
このラストシーン、笑って自らの「嘘」や「諦め」の象徴であるこの絵を肯定する彼女には、つまりはフランツと自分は完全に決別したのだという誇りが感じられた。
このシーンがくっきりとしたカラーなのもポイント。フランツのことはしっかり覚えているし、忘れもしない。それでも自分はそれを自分で殺して、別れて、自由に生きてゆくのだという意思が感じとられる。
⑹「意思」のめざめ
⑷⑸で散々アドリアンとアンナの「諦め」について語りましたが、この物語の核は、やはり何と言っても「そんな諦めた者同士が出会ってしまい、意思をもう一度取り戻す」ところだと思うのです。お互いが好きなのだと気付いてしまうところ。
そう考えれば考えるほどアドリアンとアンナの涙の意味も深まるし、涙を流すほどに恋い焦がれた相手を見つけたときには、また「諦める」しかないのだと気付かされたときに、まさに汽車の発車前に2人がそっと唇を重ねるときに、この物語は、とてつもなく美しかった。

…と、思うがままに書いてみました。
期待以上に読解の仕様がある作品ですし、これを書ききった今、それだけに色々な人の感想を読んでみたいと思います。
それにしてもアドリアン役のピエール・ニネは画面にいるだけで納得してしまうような美男子です。
アンナを演じたパウラ・ベーアは、モノクロでも伝わるほどに瞳が澄んでいて感激。アドリアンへの控えめながらも遠慮のない目線がとても良かった。

おしまい
鈴木です
良人 と書いて おっと、 とは誰が最初に定めたんだろう。とても不思議な言葉だと思う。
最近では本などでしか見かけないので、あまり耳にすることはない言葉ではあるものの。
そもそも、2人しかいない夫婦のうちの男性を「良人」と呼ぶことで、それはいわゆる男性の「大黒柱」的要素は肯定しつつも、
同時に女性、つまりは妻の方をほぼ必然的に「良くない」ように見立ててしまうことが怖い。
とても不自然でもある。
しかも、そのおかしさを感じさせないくらいに自然に使用される「良人」という言葉は、その存在感をもって無意識的に女性の行動と、女性に対する社会の許容範囲を制約できてしまう。
その言葉が生まれてから今までも、ずっとその効力は女性を支配しているようにも思える。
例えば多くある不倫報道、
不倫もまた2人でするものであるものの、多くのケースで人々に敏感にセンサーされて、非難の対象となるのは、女性。
しかも、着目したいのは、この不倫報道で女性が叩かれるとき、同性である女性も容赦ない視線を不倫した女性に対して浴びさせる。
これには、「同じ女なのに、あなただけがその不徳を許される訳がない」という掟破りの相手への一種の羨望の眼差しも感じられる。
こうして「良人」的概念から生まれた女性に対するありとあらゆる視線、呪縛のような制約は、目に見えない力として今でも色濃く残っている。
いつ女性はそれから解放されるのか。。
おそらく私が生きている間では、ないと思う。
…
すっごいフェミニスト的でしかも中途半端な大学生のような稚拙な文章ですが、、思ったこと今日のメモ。
「良さ」と「良くなさ」はどちらかが存在すれば相対的にもう一方も存在するわけで。
何かを生み出す時にはそれを覚悟して、と思いたいものの、そこまでガチガチになって生み出すものが有意義なわけはなく。。
言葉の難しさはどうしようもない!
けれども魅力的だね。
という話でした。
おわり。
鈴木です
ジムに通い始めて早1ヶ月。
ランニングマシンを愛用中。
ジムにあるランニングマシンのどこが良いかって、ふたつあって、、
① テレビがついている。
最初見たときは驚きました。普通なのかな。
字幕つけて熱中しているとあっという間に30分経ってたりする。
今日も「世界の怖い夜」を観てきました。
(敏感になっているので隣の人の動きにいちいちビクついた)
そして大事な
②張り合う相手がいる。。
これ、わかる人にはわかるし、わからない人にはわからないと思うんですけど。
隣にいるこの人より長く走ってやる!
とか、
この人のペースより早く走り続ける!
とか、その日の目標が生まれるし、
相手が隣にずっといる限りはその戦いから逃げる訳にはいかねぇ!
っていう信念が生まれる。(笑)
結構この相乗効果でジムって案外成り立っているのではないか。
そんなことを考えた夜でした。
おしまい。